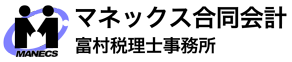スタッフブログ
【修了考査のリアル】公認会計士試験・最後の地獄を乗り越える方法
こんにちは。富村亮超(りょうたつ)です。
今日は、修了考査と言われる公認会計士試験の3つ目の難関試験について実体験も加えて解説します。
修了考査の合格率は多少の前後をみせるものの近年は70%前後を推移しています。
当然、二度と受けたくないランキングぶっちぎりの1位です。
そして、合格率が70%という絶妙に「落ちたら努力不足」感のある数値が「人並みに(ゆうて6月から)やればいける感」を出してるのも完全に罠です。
論文式と3年の実務を乗り越えた精鋭だけが母集団という地獄環境で、安定して上位7割に入るのは困難を極めます。
なのですが、法人に残ってるマネージャー以上は当然全員それを越えてきてるので、いけるやろ感がどうしてもあり、そのプレッシャーが1年という歳月をかけてJ3の心をジワジワ蝕みます。
今回は、修了考査の合格を阻む壁について、準備期・中盤期・直前期に分けて解説していこうと思います。
準備期(1月~)
一般に、修了考査の対策は1年前から徐々にスタートし、答練やCPA、TACの授業を受けながら進めていけばほぼ合格可能といわれています。
お伝えしておきたいですが、そんなものは幻想です。
監査法人には、1月から繁忙期の準備が始まり、すでに残業時間が終わってしまってる人が多数います。
逆にこの時期に暇そうに勉強なんてしていると目を付けられてわけのわからない工数の仕事が飛んできたりしますので、基本的に実務でスケジュールを全埋めすることになります。
あと普通に繁忙期の準備を怠ると繁忙期に死ぬ羽目になるのは賢いJ3諸君はご存じかと思いますのでこれはアンコントローラブルです。
従って、現実的に準備期に出来る準備は一つです。
「準備してる感を出す」
これです。
めちゃくちゃにカレンダー表を詰めたうえで、法人の修了考査アンケートには予備校の申し込みはすでに済んでいる旨報告しましょう。
監査計画調書を担当されてる方は、丁寧に進めておかれることを強くお勧めします。監査計画を半年丁寧にやれば監査論の勉強時間は半分以下で済むと思います。
繁忙期(3月~)
3~5月の繁忙期に勉強できる人は流石に変態だと思います。普通に無理です。
従って、現実的に出来ることは「次期のアサインでよく知らない新チーム(特に9月10月決算)に飛ばされないように、3月決算を全力でやってバリューを出してチームに残してもらう」です。
あと、税金・表示の担当を全力で奪いに行くのがいいと思います。
これはライフハックで、実務をしながら勉強が出来るのは
IFRS・税金・表示 このあたりです。
表示は会計学と監査論、税金は会計学と租税法にまたがっていますので、コスパもいいです。
何より出題率が高いので、これも良いです。
中盤期(6月~)
ここまでお読みの方はお分かりかと思いますが
修了考査は事実上6月~11月の中での勝負となります。
ちなみに3~5月に絶望的スケジュールを組まれている人は、6月をすべて休養に充てるくらいでもいい気がします。
なぜか?
修了考査は、繁忙期後にゆっくり勉強するという模範的社会人の幻想を打ち砕くには十分すぎるほど範囲が広いので、結局は覚悟を決めて命を懸けるしかないからです。
5月ですでに命と引き換えに職務を全うした人が懸けられるものはもう残ってないです。一回休んでください。
6月から勝負しようと考えている時点ですでに講義と答練はめちゃくちゃビハインドなので、スケジュールを守って講義を受講するのは最早不可能です。戦術を変更する必要があります。
6-7月でこれだけは見ておいた方がいいというページを貼っておきます。
このエントリを書いている方は 神 だと思います。
物理的に全範囲を学習することができないことが確定した以上、優先順位決めが勝負を分けます。
とにかくまず全体の傾向をつかんで、捨て論点を決めてください。
直前期(10月~)
急に10月まで飛んだな、と思う人がいるかもしれません。
実際、10月まで飛びます。
なぜか?
7月に新アサインが発表され、8月は監査計画に追われ、9月末に監査計画を含むあらゆる法人の締め切りが来るからです。
この間に勉強できる人は、さすがに変態です。
ですが、たまに(たまにです)この忙しいのになぜか講義と答練を進めている変態がいるのは事実です。その人たちのことは変態だと思って参考にしないようにしましょう。
ちなみに、言いたくないですが修了考査を受験するにおいて最もコントロール不能なハードルは、試験前に繁忙期を迎える決算のクライアントの担当者になるかどうかです。
9月、10月決算のクライアントにJ3(監査法人用語で3年目を指す言葉)をアサインする法人が何を考えているのか全然わかりません。
が、チームに若手を一切入れないというのもそれはそれで無理があるので、結局、誰かが犠牲になってしまいます。
優しい主査であれば休みをくれるかもしれません。
ただ、J3ともなると自分が主査(またはバリバリのコアスタッフ)もありえます。
その場合の解決策を私は持ち合わせていないので、近くのパートナーに相談するなどしてください。
10月は、本気で分かっていない論点潰しだけはしておいた方がいいと思います。
工数が無限の可能性があり、11月の計画を完全に狂わせる可能性があります。
ちなみにこの時期になると今から溜まった答練を解くというのは最早戦略としては微妙、と思います。
アウトプット練習が必要なのは、実務経験に乏しく、「試験の型」がわかっていない論文式試験の受験者であって
すでに論文式と補修所の地獄考査、日々の大量の調書でアウトプット経験を積んだ諸氏が3時間答練を時間決めて解いて得られるものって逆に何があるんですか?と強く思います。
やるとしても、租税法と会計学の連結決算だけでいいと思います。
超直前期(11月~)
ついに、命を懸けるタイミングが来ました。
まず、これは本当にあった体験記なのですが
修了考査休みに入ると、久しぶりの長期休みで、なぜか謎の余裕が出る人が一定数います。
ワンピースのアニメを全話観るなどといった血迷ったことを始める可能性がある(1年上の先輩で本当にいました)ので、とにかく、何かいったん栄養補給するにしてもせめて3日で終わるものにしてください。
私のおすすめは「からくりサーカス」です。
私は、修了考査休みに入ってすぐに、半額セールで買いだめていたからくりサーカス(初見)を全話2日半で読み切り
「命を懸けて闘う」というマインドセットを完全に仕上げました。
以降の3週間完全に「命を懸けて闘う」マインドセットで臨めたので、人生最大の出力に成功しました。
十分に参考にしてください。
冗談はともかく、計画的に勉強を進められるような変態以外は直前期の鬼詰込みだと思います。
勉強時間配分としては
会計学 20%(連結・IFRS)
監査論 20%(苦手なところを中心)
租税法 300%(全論点)
経営IT 120%(特に、財務諸表分析)
倫理規則 40%(直前暗記)
で合計500%の出力でいくのをおすすめします。
すでに直前期にさしかかった変態でないごく普通の論文式合格者の皆様に、この記事を捧げます。
それでは、がんばってください。
ちなみに私は1回目の受験と0歳児育児が重なり普通に合格をあきらめて租税法の試験を最速で退出し、帰宅して以降の試験をぶっちしてしまい
さすがに法人に怒られると思ったのですが、私の上長のパートナーが本当に応援してくれて、なんとか2回目の受験で合格することができました。
そのときのパートナーのお言葉を最後に記させていただきます。
「私も、出産と子育ての中の仕事や試験で、自分の100%が出せたらどんなに良いかと思った。けどある時気づいた。もう自分がこの先人生で自分だけのために100%出せる時間は二度とないんやなぁって。」
私は、結局最後まで本当に弱い人間でした。
最後の最後には自分の500%を出せる環境を、家族に整えてもらいました。
ありがたかったです。本当に感謝です。
富村亮超