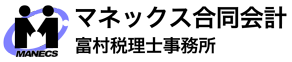スタッフブログ
AIに「置き換えられる仕事」と言われていた税理士事務所に入所して感じたこと
税理士業務はAIに代替される、という言葉の真偽
こんにちは。富村亮超(りょうたつ)です。
ここ数年、「AIが士業を代替する」という話題をよく耳にします。
監査法人にいたころは、正直「むしろもっと代替してくれよ」と思いながら、泥臭い業務に追われていました。(ちなみにほんとの直近はかなり監査実務のAI化が進んでいるらしいです。)
確かに、ChatGPTのようなAIの出現で、驚くほど多くのことができるようになりました。
しかし実際に税理士事務所で働いてみると、むしろ税務はAIが最も苦手とする分野なのではないかと感じます。
AIに相続税を計算させてみて気づいたこと
試しにAIに相続税の計算を依頼してみると、一見それらしい答えが返ってきます。
ところが中身を確認すると、適用法令の選択が曖昧で、考え方が明らかに誤っていたり、計算方法そのものが違っていたりする。
もちろん、プロンプト設計の工夫によってある程度は精度を上げられます。
しかし、どれだけ前提を正確に入力しても、AIが“納得感のある結論”にたどり着くのは難しいように思います。
その理由は、AIが「条文を読む力」しか持たず、「法を解釈する力」を持たないからです。
現場で感じる、人間にしかできない部分
私自身、まだ経験は浅いですが、業務や研修を通じて感じるのは、
税務は「数字」よりも「法の趣旨」と「人の判断」にこそ重きがあるということです。
税法とは、これまでの人類の叡智として積み上げられた「法」という体系と、
時代や社会によって変化する「倫理」や「実務の事情」とが複雑に絡み合った、極めて人間的な規範です。
それをAIが十分に理解できているとは、とても思えません。
AIは「なぜそうなるのか」という立法趣旨や判例解釈の背後にあるストーリーを再構築することができないのです。
税務計算では、単なる条文理解ではなく、
-
なぜその取扱いが設計されているのか(課税公平・二重課税の回避など)
-
実務でどう扱われているか(通達・質疑応答事例・裁決例)
といった背景の理解が前提になります。
ここが抜け落ちると、どれだけ丁寧に計算しても、現実との整合性が取れなくなります。
税理士という職業の核心
実務では、「条文上の答え」を導くよりも、事実認定・意図・経緯といった“人間的なコンテクスト”を正確に読み取る力が重要です。
AIはこの「現実 → 法形式」への翻訳が苦手で、往々にして“間違った世界の上で正確に計算”してしまいます。
また、税理士が行うアドバイスには、「正しさ」だけでなく、
依頼者の目的、リスク許容度、説明責任に適した選択肢を提示する
という側面があります。
たとえば、
-
遺産分割案による納税資金の確保
-
申告方針による将来の調査リスクの管理
-
節税策の採否(倫理・説明可能性)
これらはいずれも数値ではなく、価値判断の領域です。
AIは数理的な最適化は得意でも、「社会的に説明可能か」「人が納得できるか」という視点を持ちません。
税理士の価値はまさに、そうした合意形成のコーディネートにあります。
おわりに
AIが進化したことによって、かえって人間が果たすべき役割、人間にしかできないことがより明確になったことは実に興味深く思っています。
ただ、どのような革新的なモデルが今後出てくるかはその時になってみないとわかりません。
私が今、人間にしかできないと思っていることも、明日にはそうではなくなってるのかもしれません。ただ、確率的にはまだ時間がかかる気がする今日この頃です。